- 初めて海外旅行に行く人
- 空港での荷物トラブル(超過料金・没収)が不安な人
- 準備中に「何を機内に持ち込める?」「スーツケースは何kgまで?」と疑問を持った人
海外旅行では、荷物に関するルールをしっかり理解しておかないと、空港で追加料金が発生したり、持ち込みを拒否されて大切な荷物を没収されたりすることもあります。特に初めての海外旅行では「何を預けるべきか」「機内に何を持ち込めるのか」が分からず不安になる方も多いでしょう。
この記事では、飛行機に持ち込む3種類の荷物、「受託手荷物」「機内持ち込み手荷物」「身の回り品」の違いから、チェックインや搭乗前の流れ、到着後の荷物管理のポイントまでを整理して解説します。各航空会社で異なる重量・サイズ制限や、国際線ならではの液体物ルール、超過料金の注意点についても具体的に紹介しています。
「知らなかった」で損をしないために、この記事を通して荷物ルールの基本を押さえ、安心して旅行を楽しめる準備を整えていきましょう。
航空会社ごとの荷物ルールを確認する
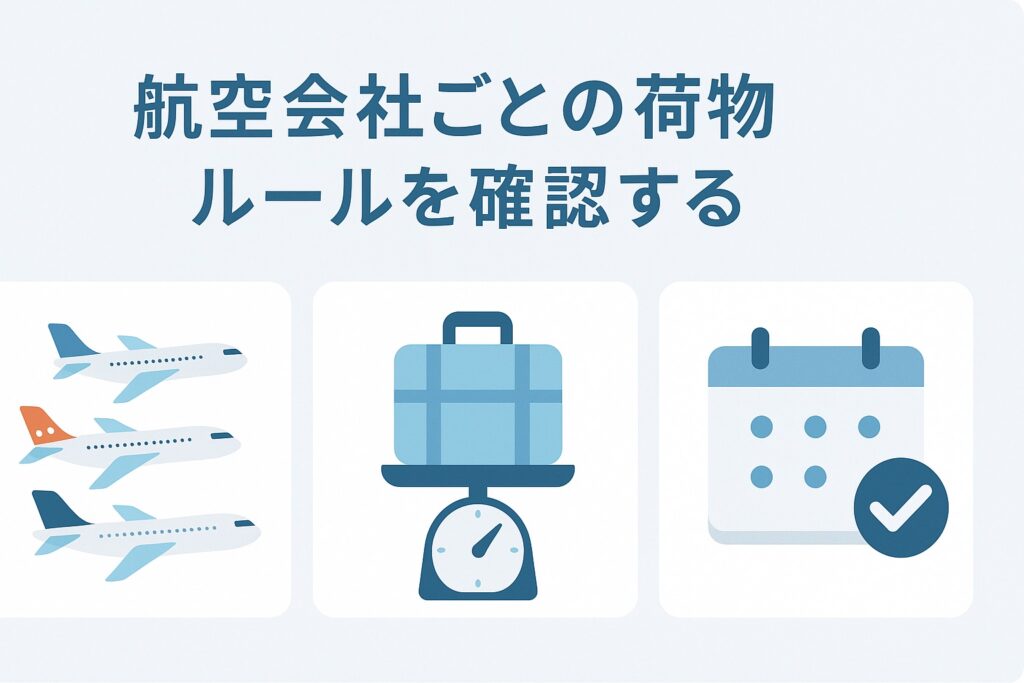
飛行機に預ける・持ち込める荷物のルールは、航空会社ごとに異なります。まずは自身が乗る航空会社のルールを確認しましょう。
特にLCC(格安航空会社)は厳しい制限や有料オプションが多いため、事前確認が必須です。
- 受託手荷物:多くのフルサービス航空会社(ANAやJALなど)は23kg×1〜2個まで無料が基本。LCCは有料になることがほとんど。
- 機内持ち込み:多くのフルサービス航空会社は「三辺の合計115cm以内・10kg前後」が目安。LCCでは「1個のみ・7kgまで」といった制限が一般的です。
- 超過料金:たとえばヨーロッパ系LCCでは「1kgオーバーで数千円追加」といったケースもあり、出発時点で重量チェックをしておくと安心です。
LCCを利用する場合、受託手荷物はウェブサイトでの事前購入をオススメします。たとえば、Peachはウェブで事前購入すると片道2,000円ですが、空港カウンターで当日購入すると3,000円になります。
参考 Peach 各種料金・手数料
飛行機に持ち込める荷物の種類

飛行機に持ち込める荷物は、大きく分けて3つのカテゴリーに分かれます。
- 受託手荷物(大きなスーツケースなど)
飛行機のチェックイン時に預ける荷物。1個あたり23kg程度が上限になることが多い。 - 機内持ち込み手荷物(リュックや小型のスーツケースなど)
座席に持ち込める荷物。搭乗後は頭上の荷物棚に収納します。身の回り品と合わせて7〜10kg以内が上限になることが一般的。 - 身の回り品(小さなハンドバッグやパソコンケースなど)
座席に持ち込める荷物。サイズ指定されていないことが多い。
この3つの分類をベースに、次から各荷物の注意点を解説していきます。
受託手荷物の注意点

空港に到着後、まずは各航空会社のカウンターでチェックインし、受託手荷物(スーツケースなど)を預けます。
受託手荷物で大切なポイントは次の3点。この3点を押さえておくだけで、空港でのトラブルを大幅に減らせます。
- 重量・サイズの制限を守る
- 危険物を入れない
- 貴重品や壊れ物は機内に持ち込む
重量・サイズの制限を守る
受託手荷物は、航空会社ごとに「重量」と「サイズ」の上限が決まっています。一般的には次のような基準です。
- 重量:1個あたり20〜23kgまで
- サイズ:3辺の合計が203cm以内
これを超えると追加料金がかかったり、最悪の場合は受託を断られることも。特にスキー板やゴルフバッグなどの特殊荷物は別ルールがあるので、必ず事前に確認しておきましょう。
重量超過のペナルティに注意
「少しだけなら大丈夫だろう」と思って重量オーバーすると、意外と高額なペナルティが発生します。日本の主要航空会社ごとの、超過料金の例は以下のとおり。
- JAL・ANA(国際線)
- 23kg超〜32kg以下:6,000円〜10,000円前後 ※運航路線によって前後します
- 32kg超〜45kg以下:20,000円〜30,000円前後 ※運航路線によって前後します
- LCC(ピーチ・ジェットスター等)
- Peachは20kg超で1,000〜3,000円
- ジェットスターなど1kgごとに追加料金がかかることも
- 当日カウンターで超過料金分を購入すると5,000円以上に跳ね上がるケースもあり
荷物が重すぎると、航空会社によっては預かってもらえないことがあります。多くの航空会社では「1個あたり32kg」を超える荷物は受託不可とされています。そのため、どうしても重くなる場合はスーツケースを分けて、1つずつの重さを32kg未満に抑える必要があります。
ただし、合計が100kgを超えると預け入れ自体を断られるケースがほとんど。大量の荷物を運ぶ予定がある方は、事前に航空会社へ確認するか、国際宅配便の利用を検討すると安心です。
乗り継ぎ・コードシェア便に注意
複数の航空会社を利用する場合は、受託手荷物のルールが異なることで、乗り継ぎの際に荷物を預けられないトラブルが起こることがあります。
特に国際線の乗り継ぎでは、最初の区間と次の区間で重量制限が違うケースも少なくありません。例えば、最初の航空会社では23kgまで無料でも、次の航空会社では20kgまでしか無料にならないケースもあります。
この差によって思わぬ超過料金がかかることもあるため、事前に利用するすべての航空会社のルールを確認しておくことが大切です。
危険物を入れない
預け入れできないものを知らずに入れてしまうと、検査で引っかかりトラブルになることも。以下のものは受託手荷物として預け入れNGです。
- 爆発物や可燃物(花火、ガスボンベなど)
- 毒物や腐食性物質
- リチウム電池を使ったモバイルバッテリー(※必ず機内持ち込み)
預け入れできないものの詳細は、各航空会社の公式サイト(参考 ANA 機内持ち込み・お預かりできないもの(国際線)・JAL 制限のあるお手荷物)や、国土交通省のリスト、政府広報オンラインを確認しましょう。
貴重品や壊れ物は機内に持ち込む
飛行機積み込み時など、スーツケースは空港でかなり乱雑に扱われることもあります。割れ物や精密機器はなるべく受託手荷物に入れないのが鉄則。どうしても割れ物を入れる場合は、緩衝材でしっかり梱包するようにしましょう。
また、パスポートや財布といった貴重品は必ず機内持ち込みにしてください。受託手荷物に入れると紛失や盗難、破損のリスクが高まりますので、管理しやすいバッグに入れておきましょう。
機内持ち込み手荷物の注意点

機内持ち込み手荷物は、フライト中に自分で管理できる便利さがありますが、サイズや重量にはルールがあります。ルールを知らないと、受託手荷物に回されて追加料金が発生することもあるので注意が必要です。
ここでは機内持ち込み手荷物の注意点について、以下の代表的な3つのポイントを整理しました。ルールを守って快適にフライトを楽しみましょう。
- サイズ・重量制限を守る
- 持ち込み可能な個数を把握する
- 液体物など禁止・制限物品を確認する
空港の保安検査では、ノートPCやタブレットをカバンから取り出したり、液体物を提示する必要があります。乗り継ぎ便では国や空港ごとに規定が異なるため、事前に確認しておきましょう。
サイズ・重量制限を守る
多くの航空会社では3辺合計115cm以内(例:55×40×25cm程度)が上限です。重さはJALやANAなどのフルサービス航空会社で合計10kg以内、LCCでは合計7kg以内が目安。
収納棚や座席下に収まらない場合は、その場で受託手荷物として預けなければならないこともあります。
持ち込み可能な個数を把握する
基本は「手荷物1個+身の回り品1個」で合計2個まで。身の回り品とは、ハンドバッグやノートパソコンバッグのような小さめの荷物のことです。
混雑した便では、収納スペースの都合でもっと制限が厳しくなるケースもあるので要注意。
液体物の制限(特に国際線)
国際線では液体類は100ml以下の容器に小分けし、1リットル以内の透明ジッパー袋にまとめる必要があります。機内に持ち込む化粧品などは小分けにして、小さめのジッパー袋にまとめておきましょう。
液体物の制限を超えた場合、超過料金の支払いでは対応出来ず、保安検査場で廃棄処分されます。飛行機内に飲み物を持ち込みたいときは、保安検査を通過したあとに空港内の自販機やコンビニで購入しましょう。
私も以前、うっかり検査前に飲み物を買ってしまい、保安検査場前で一気に飲み干す羽目になったことがあります。せっかくの旅行のスタートから慌ただしくならないよう、購入のタイミングには気をつけましょう。
なお、免税店で購入した飲み物は専用の袋に入れてもらえば持ち込み可能ですが、乗り継ぎ空港で再検査がある場合には没収される可能性もあるため気をつけましょう。
禁止・制限物品を確認
爆発物や可燃物、刃渡り6cmを超える刃物、銃器類はもちろん持ち込み不可です。
モバイルバッテリーは、160Wh未満なら機内持ち込み可能。ちなみに、160Whはスマホを5回以上フル充電できる大容量クラス。一般的なモバイルバッテリーであれば、持ち込みを拒否される心配はほとんどありません。
参考 国土交通省 モバイルバッテリーを収納棚に入れないで!~7月8日から機内での取扱いが変わります~
身の回り品の注意点

身の回り品とは、座席下に収められる小型のバッグやケースのことを指します。ハンドバッグやノートパソコン用のケース、小さめのリュックやショルダーバッグなどが代表例です。
身の回り品については、航空会社によって細かな規定が異なります。必ず公式サイトで確認し、安心してフライトを楽しめるように準備しておきましょう。
- 個数・サイズ・重量のルール
- 禁止・制限物品を確認(機内持ち込み手荷物と同じ)
- すぐ使用するものや貴重品を入れておく
- 航空会社や路線ごとにルールが違う
個数・サイズ・重量のルール
多くの航空会社では「機内持ち込み手荷物1個+身の回り品1個」の計2個まで持ち込み可能です。
サイズは座席下に収まる大きさが目安で、身の回り品としてのサイズ指定はされていないことがほとんど。機内持ち込み手荷物よりも小さなサイズに収まるようにしましょう。
重さは手荷物と合わせてJAL・ANAなどのフルサービス航空会社で10kg以内、LCCでは7kg以内といった制限が一般的です。
禁止・制限物品を確認(機内持ち込み手荷物と同じ)
身の回り品の持ち込み禁止・制限物品は、機内持ち込み手荷物と同じです。液体物なら100ml以下、モバイルバッテリーは容量・個数制限があり、危険物(火器・刃物・爆発物・スプレー缶など)は当然ながら持ち込み禁止です。
すぐ使用するものや貴重品を入れておく
身の回り品には、すぐ使用するものや貴重品を入れておくのが鉄則。特にパスポート・財布・スーツケースの鍵など、使用する機会が多くて紛失すると大きな損失になるものは、スーツケースに入れず身の回り品として管理しましょう。
航空会社や路線ごとにルールが違う
一部のLCCや小型機では、持ち込める個数やサイズにより厳しい制限が課されることがあります。また「折りたたみ傘やカメラ」を身の回り品に含めるかどうかも航空会社ごとに異なるため、事前に公式サイトを確認しておきましょう。
空港でのチェックイン・荷物預けの流れ

ここまでで「受託手荷物」「機内持ち込み」「身の回り品」と、それぞれのルールや注意点を整理しました。ここでは、実際に空港に到着してから、どんな流れで荷物を預け、搭乗へ進むのかを確認してみましょう。流れを知っておくだけで、空港での不安や戸惑いを大きく減らせます。
空港での手続き全体の流れや入国審査の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

出発ロビーに到着・案内表示を確認
空港に着いたら出発ロビーに進み、電光掲示板で搭乗予定便のチェックインカウンター番号を確認します。わからなければインフォメーションカウンターやスタッフに尋ねても大丈夫です。
チェックイン(搭乗手続き)
航空会社のカウンターでパスポートや必要書類を提示し、本人確認と便名確認を受けます。このとき搭乗券(QRコードや紙のチケット)が発行されます。
チェックインをオンラインで済ませていても、受託手荷物を預けるならカウンター利用は必須です。
受託手荷物の預け入れ
スーツケースなどをカウンターや自動預け機に乗せ、重量とサイズを測定します。規定を超えていれば追加料金が必要です。預け入れが完了すると荷物にラベルが付けられ、手荷物引換証(バゲージタグ)が渡されます。現地到着後、バゲージタグが荷物の受け取りに必要な場合があるので、必ず保管しておきましょう。
その他の確認事項
マイレージを付けたいときはカウンター・チェックイン機でマイレージに対応しているカードを提示しましょう。
また、乗り継ぎ便がある場合は、最終目的地まで荷物が自動で送られる(スルーバゲージ)か、途中で受け取って再度預ける手続きが必要かを必ず確認してください。
保安検査・搭乗ゲートへ
荷物を預け終えたら保安検査場に進みます。ここで機内持ち込み手荷物検査と身体検査を受け、通過後に搭乗ゲートへ向かい、出発まで待機となります。
乗り継ぎ・国際線で注意すべきポイント
- 再チェックインが必要な場合
アメリカやカナダを経由する場合は、一度荷物を受け取って再度預け直す必要があります。入国審査もあるため、乗り継ぎ時間は最低2時間以上を確保すると安心です。 - 免税品や液体物の制限
経由地によっては免税店で買った酒や化粧品でも再検査で没収されることがあります。「STEB(免税封印袋)」に入れてもらえば通過しやすいですが、国ごとにルールが違うので注意が必要です。 - セキュリティ基準の違い
経由地によっては電子機器やバッテリーに関して特に厳しく検査されることがあります。中東やアメリカを経由する路線では、ラップトップの追加検査などを想定しておきましょう。
現地での注意点

飛行機が到着してから空港を出るまでの間も、荷物に関する注意は欠かせません。降機時のマナーや手荷物の受け取り、破損・紛失時の対応などを知っておくだけで、現地でのトラブルをぐっと減らせます。
ここでは、到着後に押さえておきたい荷物管理のポイントを整理しました。
ヨーロッパではロストバゲージが珍しくないため、着替え1日分と必需品は機内持ち込みに分けておくのがおすすめです。
預け荷物の受取
到着後、入国審査が終わると、受託手荷物を受け取るために空港の「手荷物受取所(Baggage Claim)」に向かいます。手荷物受取所は便ごとに分かれており、電光掲示板に出発地・便名が表記されているので、自分の便名のベルトコンベアを確認し、荷物が出てくるのを待ちましょう。
紛失・間違い防止
ベルトコンベアから荷物を取る際には、手荷物預け証の番号と照合するのを忘れないようにしましょう。同じようなスーツケースが多いため、目印(タグやベルト)を付けておくとスムーズです。
荷物タグ(手荷物預け証)は、荷物を受け取るまで必ず保管してください。もし自分の預けた荷物が見つからない場合や間違えそうになった場合は、すぐに空港スタッフに相談するのが鉄則です。
また、出口と受取所が分かれている空港では、誤って手荷物受取のない出口から出ると戻れなくなってしまう場合もあるので注意してください。
荷物の状態チェック
荷物を受け取ったら、必ず破損や開封痕がないか確認してください。異常があれば、その場で空港の手荷物サービスカウンターに届け出ましょう。後からでは、保険などの補償対応が難しくなる場合があります。
空港出口での注意
混雑する空港出口付近はスリや盗難のリスクが高まる場所です。荷物の置き忘れにも要注意。受け取った荷物を必ず自分で確認し、出口を出るまでしっかり持ち歩きましょう。
まとめ
海外旅行では、荷物に関するルールを正しく理解しているかどうかで、旅の快適さが大きく変わります。
受託手荷物・機内持ち込み手荷物・身の回り品の基本的な区分を押さえ、航空会社ごとのサイズ・重量制限を事前に確認しておけば、空港での思わぬ追加料金やトラブルを防ぐことができます。
また、チェックインや搭乗前の流れ、到着後の荷物受け取り・管理のポイントを把握しておくことで、不安を減らしスムーズに行動できます。特に初心者の方は、事前準備とちょっとした工夫が安心感につながります。
旅行中の荷物は、単なる「持ち物」ではなく、旅そのものを支える大切な存在です。ぜひ今回の内容を参考にして、荷物に関する不安を解消し、より快適で安心できる海外旅行を楽しんでください。
あなたの旅が、安心とワクワクに満ちたものになりますように。
出発前準備をまとめて確認したい方は、こちらの記事がお役に立ちます。





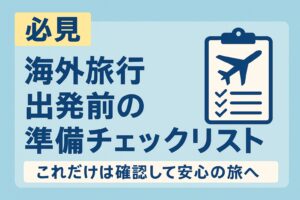
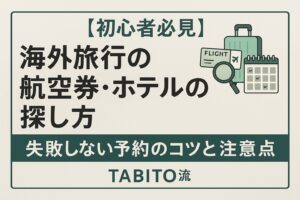

コメント